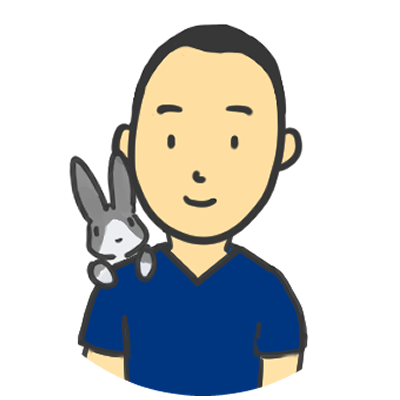マイクの選び方まとめました
ご覧いただきありがとうございます。この記事を書いたTEAと申します。
当記事における前提:オンライン上にて交流の際に使用したり、あるいはお仕事等での通話の際にご利用になることを前提としました。
よって今回オススメとして記載している内容は、人の話す声を拾うことに向いているマイクを想定しています。
楽器を使って演奏を収録する等の目的でマイクをお探しの場合には、解説内容がご期待に沿えない可能性がありますので、その点はご了承ください。
この記事を読んでいただければ、今のご自身の環境に合ったマイクの選び方がある程度わかるようになると思います。
解説についてはマイク選び初心者の方にも理解しやすいように、可能な限り簡単な表現になるよう意識しました。
ただ私の文章力の至らなさもあり、どうしても機械の解説の文章は難しく感じやすいと思います。
そこで、大まかなマイク選びのポイントだけ知りたい方のために、「結論」という項目に要点を記載しました(このあとすぐの見出しの記事です)。
本記事はまずこの「結論」だけ読んでもらえれば大丈夫です。
その上でよく解らないところやより詳しく知りたいことがあれば、目次から各項目へご移動してもらうと効率よく読めるかと思います。
「結論」以降の項目については、大見出しに重要度を★の数で表示しました。内容は以下のようになっています。
・★★★★:マイクの分類なので、特性を知っておいて欲しい項目
・★★★ :マイクの音質に影響したり、便利で快適に使える機能の説明
・★★ :マイクの保護や取り回しの便利さが欲しい場合に役立つ項目
・★ :マイクの仕様・性能表示を読めるようになるための項目
★★と★のところは余裕があったら(もしくは複数のマイクの比較でどうしても悩んだ時に、最後の決め手探しで使う感じで)読んでみるくらいで充分だと思います。
特に★の内容は仕様や数値の解説なので、読んでみたい方だけどうぞ!
この記事をきっかけに、あなたに合うマイクがみつかりますように。
そして1人でも多くの方の魅力あるお声が、しっかり伝わる環境が整いますように。
結論

これより初心者向け・マイクの候補の絞り方をお話しします。
まずは次の0~4のSTEP順に、どの選択をしたか書き出してみてください。
すべて書き出したあとで候補をネットで調べてもらうと、どんなマイクが向いているか整理できると思います。
様々なマイクごとでどのように聴こえ方が違うのか、気になる方はこちらの記事も参考にしていただければと思います。

検索の際には、価格.comやAmazonなどのサイトでみると、人気商品もわかりやすいと思います。
それでは、順番に条件を書き出していきましょう。
STEP0:大前提として…
無線(ワイヤレス)接続より有線接続を選ぶ!
有線接続(実際に機器同士をケーブルで繋ぐ)を選んだほうがいい理由は、無線接続だとマイクとパソコンとの通信のトラブルや、使用中のマイクの電池切れといった問題が生じる可能性があるからです。
シンプルに有線接続にして接続トラブルを回避できるほうが、使用中の心配を確実に減らせます。
接続方法がUSB端子のものを選ぶ!
有線でのマイクの接続方法は4種類くらいあるのですが、パソコンやスマホなどに接続してすぐ使えて音質でもよいので、USB接続を選びましょう。
他の接続方法だと、オーディオインターフェースという機器や専用のケーブルなどが必要になったりするので、知識も費用もさらに必要になってしまいます。
USBには主要な接続タイプにAとCがありますので、マイクよりもお使いのパソコンなど機器側の差込口を確認しましょう。スマホやタブレットにもつなげられるので、USB-Cで差し込めるとさらに便利です。
※USBにはタイプごとにA・B・Cという形状に分かれます。
四角いのがA、台形っぽいものや複雑な形なのがB、楕円形なのがCです。
お使いの機器の差込口に合うものを選んでください。
それでは、いよいよマイク本体のタイプを決めていきます。
STEP1:まずはマイクをどう使うかを決める
マイクには
・スタンド(据え置き):台座で固定して使う
・ハンドヘルド:カラオケなどのように手で持って使う
・ヘッドセット:ヘッドホンとマイクが一体になったタイプ
・ラべリアマイク(ピンマイク):服などにクリップで留めて使う
・ガンマイク:カメラに取り付けたり、ポールに取り付けたりして使う
などの種類があります。
この中で、zoomやバーチャルオフィスなどにパソコンやスマホ経由で入って使うのにちょうどいい候補は以下になります。
・スタンド :マイクを置く場所(机やテーブル)がある
:高音質や多機能なマイクを選びたい
・ヘッドセット :マイクの置き場がない
:通話中でもパソコン作業をどんどんやりたい
・ラべリアマイク:パソコンから離れて移動している時にも使いたい
:屋外でも使いたい
:できるだけ目立たないマイクがほしい
当て嵌まる特徴があれば、そのマイクを中心に調べましょう。
(ハンドヘルドは手持ち前提で、ガンマイクは初心者向けではないマイクなので、この2つは今回候補から外します)
※一部のスタンドマイクには、購入時にスタンド(マイクの台座のこと)が入っていないものがあります。
スタンドマイクを据え置きで利用する方は、スタンドが付いてくる製品を選ぶ(別売りやセット販売もあります)か、マイクアームの購入をご検討いただくといいと思います。
STEP2:マイクの種類(型)をさらにしぼり込む
マイクの種類が決まったら、さらに型を決めましょう。
マイクはダイナミックマイクとコンデンサーマイクの2つの型に分けられます。
それぞれに特徴があるのですが難しい話になるので、マイクを使う場所が車の音や家族の声など色々な雑音が入りやすいかどうかでしぼり込むのがおすすめです。
◎雑音がわりと入りやすい環境で使う人:ダイナミックマイク
◎使用時に雑音の少ない静かな環境がある人:コンデンサーマイク
ここまでで、マイクの種類をある程度限定できたと思います。
STEP3:マイクの機能のリストアップ
ここからは、マイクの細かな機能があるかどうかを調べるときに、特に優先してチェックするといい項目をあげておきます。
次の番号順に書き出すリストを作っておきましょう。
①指向性(しこうせい)が「単一指向(カーディオイド)」になるか
マイクが音を拾いやすい方向のことを指向性(極性パターンと表現されている場合もあります)と言い、次の3パターンがあります。
・単一指向(カーディオイド)
・無指向または全指向(オムニ)
・双指向(フィギュア8)
この中で、できるだけ単一指向で使えるものを選びましょう。
※ヘッドセットやラべリアマイクを選ぶ方は、単一指向が非常に少ないと思いますので、無指向のものも候補に入れることになります。
単一指向というのは、マイク正面の角度から来る音を集中的に拾ってくれることを言います。
無指向(全指向)だと全方向からの音を拾うので、ノイズがより入りやすくなってしまいます。
※詳しく知りたい方は、あとで「指向性」の項目をお読み下さい。
②あると便利な「音声ミュート(消音)」
音声ミュートは、オンにすると音声を一瞬で消してくれる機能です。
そのマイクごとの専用ソフトウェアで操作するものと、スイッチやボタンやパネル、センサー式など色々あります。
触れる際の雑音が入りにくいので、タッチパネルやタッチセンサー式のものが便利です。
③あると便利な「ゲイン調整」
ゲイン調整は、マイクに入った音声信号を増幅する機能で、音の聴こえ方の大きさに関与します。
ゲインを上げる
→ 相手には大きな音になって聴こえるが雑音も入りやすくなる
ゲインを下げる
→相手に聴こえる音も小さくなりますがノイズも入りにくくなる
※正確なゲインの役割については、別途「ゲイン調整」の項目をお読みください。
ほとんどは専用のソフトウェアで設定できるようになっていますが、まれに安いマイクだとゲイン調整できないものもあるので注意です。
物理的に手で動かして調整するタイプだと、ツマミやノブになっているタイプとパネルになっているタイプが多いです。
単純に手元で相手への聴こえ方の調整ができるので、ライブ配信や音声通話の用途にはこの機能があると便利です。
STEP4:予算について
最後に大切な予算について、アドバイスをお伝えします。
色々なマイクを試してみての感想ですが、大体8000円あたりから音質もよく、いくつか機能が付いているマイクが出てくる印象があります。
初めて選ぶなら1~4万円くらいの価格帯のところに、多機能&高音質のマイクがみつかりやすい印象です。
私も色々なマイクを試してみて、現在は購入当時4万円くらいしたSHUREのダイナミックマイクを使っています。
音質・機能性ともに満足度◎
マイクは高価なものになると数十万円とか(中には100万円を超えるものまで!)ありますが、極端に高価なものは一般人の使用環境では性能が引き出せず勿体ないと思います。
おまけ:それでもまだ迷ったら…
マイクの候補は似たようなものがたくさん出てくることがあると思います。
どうしても決めきれない場合に、有名ブランドでしぼり込むという手段がありますので、マイクの有名ブランドを一部ご紹介しておきます。
※これ以外のものがダメというわけではありません。マイクのブランドも非常に多いので、あくまで一部のみのご紹介です。
海外の有名ブランド(古くからある)
・シュア(SHURE):アメリカ
・ゼンハイザー(Sennheiser):ドイツ
・アーカーゲ―(AKG):オーストリア(現在はアメリカ)
・ノイマン(Neumann):ドイツ
海外の有名ブランド(比較的新しい)
・ロード(RODE):オーストラリア
・ハイパーエックス(HyperX):アメリカ
・レイザー(RAZER):アメリカとシンガポールに本社
日本の有名ブランド
・オーディオテクニカ(Audio-Technica)
・ソニー(SONY)
・ヤマハ(YAMAHA)
・マランツ(Marantz):アメリカ→日本企業の子会社に
ちなみに、上記の中で売れ筋とか人気商品で名前が出てきやすいものは、
ダイナミックマイク:SHURE、Audio-Technica
コンデンサーマイク:AKG、RAZER、HyperX、Audio-Technica
といった感じです。
まとめ
ここまで順番にご説明させていただきましたが、チェックする項目を再度確認しましょう。
STEP0:有線接続でUSBで接続する製品にする
STEP1:マイクの種類を決める
・スタンド(据え置き)→マイクスタンドが同梱されるか確認
・ヘッドセット
・ラべリアマイク
STEP2:マイクの型を決める
・ダイナミックマイク
・コンデンサーマイク
STEP3:各種機能をチェックする
・単一指向性が選べるか
・音声ミュート
・ゲイン調整
STEP4:予算でしぼり込む
おまけ:ブランドでも絞り込んでみる
以上をふまえて、仮に私が皆さんへオススメするとしたら…の設定はこちら。
◎ノイズ対応を中心に考えた構成なら
・有線接続でUSBで接続
・スタンドかヘッドセット
・ダイナミックマイク
・単一指向性
・音声ミュートのタッチセンサーがついているタイプ
(ダイナミックマイクのゲイン調整は、専用のソフトウェアで制御するものが多いので、マイク本体に操作するものがなくてもOK)
・候補に迷ったら…SHURE、Audio-Technicaなどがおすすめ
◎ノイズの少ない静かな部屋で使えるなら
・有線接続でUSBで接続
・スタンド、ヘッドセット、ラべリアマイクどれでも可
※できれば据え置き推奨
・コンデンサーマイク
・できるだけ単一指向が選択できるもの
※ヘッドセットやラべリアマイク(ピンマイク)だと無指向の製品が多く、単一指向は選べない可能性が高くなります。その場合は無指向を選ぶことになります。
・音声ミュートとゲイン調整が操作できる製品
(ただしゲイン調整は専用のソフトウェアで制御も可能なので、こだわり過ぎなくてもOK)
・候補に迷ったら…AKG、RAZER、HyperX、Audio-Technicaなどがおすすめ
各チェック項目が決まったら、ネットの検索で調べてみましょう。
具体的な例としては
「スタンド ダイナミックマイク USB」
「ヘッドセット コンデンサーマイク USB」
といった感じで、
「マイクの種類 マイクの型 USB」
といったキーワードで入れてみてください。
そこで出てきたマイクから、さらに各機能の有無や価格をみて絞り込んでいく感じになります。
いかがでしょうか?
これでもマイクがたくさん出てきて、迷うかもしれません…。
もちろん上記の条件から外れるものがあっても大丈夫です。
あくまで一例なので。
とにかくまずは上記のような基準で、マイクを探してみるといいかなと思います。
(難しく感じるようでしたら、ごめんなさい)
まずはマイク探しに、チャレンジしてみていただけたら嬉しいです。
ちなみに当ブログにてオススメしているマイクの最新機種は、
ダイナミックマイク:MV7+
コンデンサーマイク:HyperX Quadcast 2s
各種マイクの聴こえ方の違いを知りたい方は、下記の記事もご覧ください

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!
これよりは、マイクの種類や各種機能・性能などについての詳細な解説になります。
長文で難しい内容も多いので、調べたい項目があったらお読み下さい。
マイクの型と種類(重要度:★★★★)
マイク選びの際に必須となる分類の話です。用途に応じて必要なものが選べるように、最初に知っておくべき特徴をご説明します。
コンデンサーマイク型
・コンデンサーと呼ばれる、電気を貯蔵したり放出したりする電子部品を利用しているマイクです。
・コンデンサーの中に貯めてある電気の変化を信号にすることで音を再現するため、必ず電源が必要になります(だからUSBで使えるものが多い)。
・コンデンサーマイクは感度(感度とは、小さな音にも反応して電気信号として変換できるかどうかといった意味だと思って下さい)が高く、小さな音も拾ってくれる特徴があり、クリアで音の再現性の高いマイクになります。
・その一方で設定次第では小さな雑音なども拾ってしまう可能性が高くなります。例えば通話中にもキーボードで文字を打ったりしながら使うことが多い場合には、静音タイプのキーボードを用意しないと、カチャカチャした打鍵音が入りやすいです。
・精密部品なので湿気やカビ、衝撃などにも弱いという傾向があります。
・使わないで収納しておく際には、乾燥剤などを一緒に入れて湿気・カビ対策をする必要が出てきます。
周辺の環境音などが比較的入らない静かな場所で使うのであれば、コンデンサーマイクのほうがよりクリアで良い音が再現しやすいです。マイクから多少離れても比較的しっかりと音を拾ってくれるマイクです。
ダイナミックマイク型
・振動版とコイルという部品が物理的に振動することで、音を電気信号に変えるタイプのマイクです。
・電源がなくても電気信号を生み出せるので、USB以外の接続方式で使われているものが多いです。(逆に、USB接続で使えるものが少ない)USB以外の接続方式では、オーディオインターフェースと呼ばれる機器を介して音声信号を適切に処理する必要があるので、注意が必要です。
(※正確には、USB接続で使えるダイナミックマイクにはマイク内部に小型のオーディオインターフェースが内蔵されているということです。)
・コンデンサーマイクに比べて感度が低いので、周辺の雑音を拾いにくいという特徴があります。このため、マイク近くでキーボードで文字入力する頻度が多い場合でも、コンデンサーマイクよりは打鍵音(カチャカチャした音)の強さが少し減ります(完全に入らないマイクはほぼ無いので、そこは期待しすぎないほうがいいです。)
・構造がシンプルなので壊れにくく丈夫で、衝撃などにも強いです。コンデンサーマイクに比べれば湿気やカビにも強いので、保管が簡単で持ち運びにも便利という特徴があります。
同居の家族の声が気になるとか、道路に近いので車の走行音が気になる等、環境音が入りやすい場所でお使いの際には、ダイナミックマイクのほうがノイズの少ない音声になります。
マイク使用中にキーボードで文字入力が多いという人にも向いています。
ただしダイナミックマイクは音をしっかり拾える範囲が狭くなるため、横を向いて話したり、マイクから距離が離れた場合などでは、一気に聴こえにくくなるという傾向があります。
上手に口元近く(マイクにもよりますが、10~20cmの範囲内くらい)をキープできるように、マイクスタンドやマイクアームで位置を調整できる環境が重要なマイクになります。
ここからはさらに、マイクを細かく分類して特徴を挙げていきます。
スタンド(据え置き)

据え置きで使うタイプのものです。初めからマイクスタンドが付属しているものもあれば、別途購入が必要な場合もあります。
マイクは振動に弱いため、机に置いて使う場合だと同じテーブル上にあるものの音(例えばマウスのクリック音やキーボードの打鍵音)をけっこう拾う可能性があります。
スタンドから外してマイクアームに付け変えると、ノイズの音源から遠ざけることもできるので、マイク使用中にキーボードで入力する頻度が多い方は、マイクアームの導入も検討する価値があると思います。
ハンドヘルド

手で直接持って使うタイプのマイクです(カラオケなどで持ったことのあるマイクのイメージです)。グリップ部分を直接手で触れてもノイズが入りにくいように作られています。
ダイナミックマイクのタイプが多く、口元に対して正しい方向と角度で持たないと、たちまち音が拾いにくくなる傾向があります。
ヘッドセット

ヘッドホンとマイクが一体になったタイプのもので、マイク位置が口元と常に一定の距離で固定された状態を保てる(顔の向きを変えたり、移動したりしても常に音量が安定する)という利点があります。
マイクが離れている分、キーボードの打鍵音も比較的入りにくいです。
逆に言うとマイク位置が口元に近いため、呼吸音や口元からのノイズが入りやすかったり、どうしてもマイクの集音部品が小型になるので、据え置きで使うタイプのマイクに比べると少しこもりがちな音になる傾向があります。
あと、ヘッドホン部分のバンドやイヤーマフで圧迫されるため、髪型が気になる方には向かない可能性が高いです。
またWEBカメラをオンにして顔出しでやり取りする場合、見た目では一番目立つタイプのマイクなので、仕事感が出ると思います。
キッチリした感を演出したい場合には合いますし、逆に柔らかい印象を与えたい場合には、別のマイクの選択がいいかもしれません。
ラべリアマイク(ピンマイク)

主に衣類にクリップなどで固定して使う小型マイクです。屋内・屋外を問わず移動することの多い場面で活躍するマイクです。
また、ヘッドセットでは重さを感じてしまったり、見た目の面でもマイクをできるだけ目立たなくしたい方にとっては、ピンマイクがオススメになります。
無指向のものが多いため、身体近くで生じた音は拾ってしまうことがあります。
特に身体が動いた場合に、衣服でこすれてガサガサというノイズを拾ってしまうこともあるため、付ける位置に注意が必要です。
衣服などに付けるタイプのマイクを広義でラべリアマイクと呼び、そのなかでも針状のタイプのものをピンマイクと呼ぶのが本来のようです。
ですが、現在ではどちらの意味でも通じる場合が多いようなので、呼び方についてはそれほど気にしなくてもいいかもしれません。
ガンマイク

細長い棒状の形のマイクです。
スタンドに付けるものや、カメラに取り付けるものなどがあります。
音を拾う範囲がかなり狭く、周辺のノイズがより入りにくい構造でさらに遠方の小さな音までも拾いやすいものもあります。
人の話し声はもちろん、屋外での自然の音を収録したい際などに用いられることが多いと思います。
知識がある程度求められるマイクだと思いますので、初心者の方が最初に選ぶにはあまりオススメしません。
接続方式
マイクの接続に使われる端子は、次のようなものがあります。
・USB端子
・XLR端子(キャノン端子と呼ばれる場合もあります)
・フォーン端子
・ミニプラグ端子

このうちUSB以外のものは、まずパソコンに直接つなげられません。ケーブルをパソコンにつなぐにあたり、特殊な変換端子や間を取り持つ機器(オーディオインターフェース)が別途必要になります。
ミニプラグ端子はパソコンなどの機器によっては差込口がありますが、ノイズを多く拾いやすく、音質はそれほどよくない傾向があります。
よって、USB端子で接続できるものが一番使い勝手が良いです。
オーディオインターフェースはいくつもの会社が出していて金額の幅も広く、また機器ごとの特徴もかなり異なるため、初心者が選ぶのはかなり大変だと思います。
USB接続で使えるマイクの中でも、特にパソコン側をUSB-Cで使えるようにすると、幅広い機器につないで使えて便利です。
各種機能(重要度:★★★)
この項目は、マイクの各種設定に影響する項目です。マイクをより快適に便利に使えるような機能を挙げたので、説明していきます。
指向性
マイクが音を拾いやすい方向のことを指向性と言います(極性パターンと表現されている場合もあります)。
特にコンデンサーマイクの多機能型で切り替えができるものが多いです。
指向性には次のものがあります。
・単一指向(カーディオイド)
・双指向
・無指向(全指向)
このうち単一指向には、カーディオイドからさらに音を拾う範囲を絞り込んだスーパーカーディオイドやハイパーカーディオイドと表現されるものもあります。
単一指向というのは、マイクのある一定の角度から来る音を集中して拾ってくれることを言います。
側面や背面からの音はだいぶ拾いにくくなりますが、まったく拾わないわけではありません。特にコンデンサーマイクは、単一指向でも意外と離れた位置からの音も拾っていたりします。
ちなみに全方位からの音を拾うものを無指向あるいは全指向(オムニ)、正面と背面のみの音を集中して拾うものを双指向(フィギュア8)と言います。
双指向は複数人数で1本のマイクを使う場合などでしか使う機会がありません。
無指向は全方向からの音を拾うので、ノイズがより入りやすくなってしまいます。
自分自身の音声を良くするという点では基本的には単一指向で使えると良いと思います。
なお、指向性とは少し異なりますが、一部のマイクには「ステレオ」というという切替が含まれていることがあります。
ステレオは一見すると双指向や無指向に似ていますが、左と右のそれぞれから入ってくる音を区別して、音を立体的に収録しようという、どちらかというと収録方式のことを示す切替スイッチだと言えます。
音声ミュート
音量(ボリューム)を一瞬でゼロにする機能です。
音を消したくなった際にボリュームをゼロにしたり、そこから適切な音量まで戻す手間を省けます。
パソコンなどソフトウェア上でミュートにする場合と、マイク本体にスイッチやボタン、タッチパネル、タッチセンサーなど様々な形状があります。
とっさの時にマイク本体でミュートできるほうが便利で、さらにマイクに触れるためタッチセンサー式のものが一番ノイズが入らずに使えると思います。
感度の高いタッチセンサーだと、センサー部に指が触れない距離(表面から2~3mmくらい離れていても)でも反応してくれるものもあります。
なお、ovice(バーチャルオフィス)やzoomなどを使用中にマイク側で音声ミュートにした場合、マイクによって画面表示上は音声ミュートになるものとならないものがあり、画面上では音声ミュートがOFFになっているのに、マイク側がミュートONだと音は入らない…というケースもあります。
これについては一度テストしておくのがオススメですが、画面上で音声ミュートが入っていなくてもマイク側でOFFにできると、相手に気付かれずに一瞬離席したりくしゃみしたりができるので、便利です。
マイクでミュートになっているのに気付かず、1人でしゃべってしまうこともまれに起こります…(笑
ゲイン調整
ゲインは、マイクに入ってきた音声を電気信号に変える際に、信号を増幅してハッキリとした音にさせていく役割があります。
ゲインを上げると小さな音も大きく聴こえるようになり、大きな音はより大きく聴こえるため、音量(ボリューム)と同じように感じやすいですが、本来その役割には違いがあります。
ゲインは信号を増幅するので、上げすぎると音が割れる(音が歪んでおかしくなる)状態になってしまいます。
※音が割れた状態は、Youtubeなどで配信者が大声を出したとき、音がバリバリビリビリしたような感じになっているのを思い出していただければと思います。
一方でボリュームはもともとの信号はそのまま、音の大きさだけを増やすので、ボリュームを上げ続けても音が割れることがありません。
ちょっと乱暴な比喩ですが、イメージとして…
「めんつゆ」があったとして、つゆの濃度を3倍とか5倍とかに濃縮していく(汁の量は変わらないが、味がどんどん濃くなる)のがゲインを上げること。
めんつゆをそのまま量を注ぎ足して多くするのがボリュームを上げること(汁の量は増えるが、味の濃さは変わらない)…みたいなイメージです。
ゲインは上げ過ぎると、背後で「サーッ」というノイズ音(ホワイトノイズ)が入ることがあります。
ホワイトノイズが入らず、かつ音が割れない適切な音声の大きさになるところを探して、あとは
付属品(重要度:★★)
マイクを保護したり、ノイズを低減する役目を持った部品の解説項目です。無くてもマイクは使えますが、あったほうがより安心・快適に使えるようになるものをここで説明していきます。
ショックマウント

ショックマウントはマイクを振動から守る役割があります。
ですので、キーボードを打ったときやマイクを少し動かしたときなどに、マイクに伝わる振動を軽減してくれます。
もちろんショックマウントがあっても振動を完全に防いでくれる訳ではないので、過剰な期待はしてはいけません。
特にコンデンサーマイクは音をしっかりと拾いやすいので、ショックマウントのない状態だと、想像以上にカタカタと振動する音を拾ってしまいます
(カタカタ…という音が、ガタゴト・ボンボン鳴るイメージです)。
ポップフィルター(ポップガード)
ポップフィルターは、息がマイクにぶつかるときのノイズを軽減してくれる効果があります。
マイクに向かって話しかけるとき、特にパ行やバ行など息が強くあたりやすい発音では、「ボッ」とか「バフッ」といった感じの音が入ってしまう場合があります。ポップフィルターはこうした吹き付けた息がマイクに当たるのを弱めてくれる役割があります。
もちろん、そうしたノイズを完全に防げるわけではなく、あくまで少し減らすという程度です。
ただポップフィルターには単にノイズ対策だけでなく、マイク内部の精密な部分に息が直接当たらないようにすることで、唾液や吐息の湿気から機械を守り、故障を減らすという効果もあるとされます。
そのため、マイクを長く使えるようにするためには、あったほうが嬉しい部品になります。
スポンジ状・布製・金属製のものがあり、マイクに内蔵されているタイプのものは基本的にスポンジ状です。
スタジオ収録の様子などの動画で、マイクの前に円盤状の金属部品がついているのを観たことがある人も多いのではないでしょうか。
スポンジと布製は厚み次第で効果が変わりますが、マイク内蔵のスポンジは厚みがあまりないことがほとんどで、外側にさらにポップフィルターを重ねて着けて使用するケースもあります。
ただ、取付位置や取り付け方は専用のものを除くと意外と難しかったりもしますので、注意が必要です。
ポップフィルター以外に、ポップガードやウインドスクリーンという名称で呼ばれる場合もあります。
マウントアダプタ―
マイクを使う方の中には、マイクアームを使用したいと考えている方もあるかと思います。
そんなときに必要になるのが、マウントアダプタです。
取り付けはマイク側の固定部のネジを回して取り換えるだけ…なので、難しくはありません。多くの場合、付属のマイクスタンドから取り外して代わりにマウントアダプタを付けるだけです。
マウントアダプタは、ほとんどが3/8インチと5/8インチという規格に適合していますので、マイクアームをご利用になる場合はご確認ください。
この2つの規格に適合するなら、大抵のマイクアームで使うことができるので安心です。
今はマイクアームを使用していないけど、将来的には導入を検討したい…という方にとっても、便利です。
内蔵LEDライト
いわゆる「ゲーミングマイク」と言われるようなタイプによくみられる、マイク本体の一部が様々な色に光るものです。
よく宣伝用の画像では虹色とか派手に光っていることが多いですが、マイクごとの専用ソフトで色を細かく設定できるものが多いので、マイクによっては最初から単色で光るよう固定されているタイプを除けば色も自由に設定できたり、単色だけにしたり、光らせないという設定もできたりします。
光らせ方のパターンもマイクに内蔵されているLEDの数で様々なので、ライティングを楽しみたい方は動画などで光り方のパターンを調べてみるといいかと思います。
内蔵ヘッドホンジャック
マイクが拾った音声をリアルタイムに自分の耳で聴く(モニタリングと言います)ことができるように、ヘッドホンなどの差込口がある場合にヘッドホンジャックの表記があります。
一般的なイヤホンやヘッドホンが差し込める、3.5mmステレオミニジャックの差込口が多いように思います。

マイクの側面や底面などに差込口がついていて、そこにヘッドホンやイヤホンの端子を差し込むことで、自分の音声やPCからの音声などを聴くことができます。
モニタリングができるタイプのマイクは、マイクが拾う音量とPC側から聴こえてくる音量の比率を変えることができる場合が多いので、シンプルにヘッドホンで音を聴くためのものとして使えます。
モニタリングの機能は、会話よりも音楽の収録などのほうが使われることは多いかもしれません。
ただ、オンラインで会議する際などイヤホンをしているときには、自分の声が聴こえたほうが意外と話しやすいこともあります。
マイクアーム

マイクを吊るすような形で固定することができる道具です。机や柱にクランプというネジで締める金具で固定するものが多いです。
マイク購入時にセット販売しているものも探すと出てきます。
マイクを口元近くに持ってきやすい(=適した距離で使いやすい)ことはもちろん、マイクに伝わる振動を減らしたり、キーボードからマイクを離れた位置で保持できるので、カチャカチャした打鍵音を拾うのを少し減らすことにも役立ちます。
マイクアームを使用する場合、マイク本体の重さを確認しておくことが大切になります。
あまりに重たいマイクの場合、アームが適した位置を保てず垂れ下がってきてしまうこともあるためです。
当ブログでオススメしているマイクアームはこちら
性能表示(重要度:★)
マイク購入時などで、性能について書かれているものの一部の意味を理解できるようになりたい時にお読み下さい(この項目の内容は、知らなくてもマイクは充分扱えます)。
より高性能なマイクの購入を考える際に使えると思います。
製品によってすべて明記されているわけではなかったり、単位や表現も微妙に違う場合もありますので、その点についてもご承知おきください。
感度
マイクがどこまでの音を電気信号に変えるかの度合いを示したものです。
単位はdB(デシベル)で表示されます。
・感度が高いものは小さな音もよく拾うが、ノイズも拾いやすい
・感度が低いものは音を拾う範囲が狭くなるが、ノイズは入りにくい
という特性があります。
感度の表示は-30dBとか-60dBなどのように表記されます。この数値が0dBに近いほど感度が高く、数値がマイナス側に大きくなるほど、感度が低いことを示します。
感度 高 >0dB>-30dB>-60dB> 低
感度は高ければ高いほど良い…と思いがちですが、感度の高いマイクはノイズが入りやすいだけでなく、ある程度大きな音声だと音が割れる(歪む)可能性も高くなってきます。
コンデンサーマイクのほうがダイナミックマイクより感度が高いです。
サンプルレート・ビット深度
マイクが集音した音波を電気信号に変える際に、その音の情報量や密度をどの程度まで細かくするか…を決める数値です。
サンプルレート、ビット深度ともに数字が大きいほど、より緻密な音声データになっていると言えます。
画像で言えば解像度みたいなイメージです。
解像度が高い画像はファイルサイズが大きくなり容量が重い…というのと同じで、サンプルレートとビット深度が深いものの場合、音の情報はより緻密なものとして記録される代わりに、ファイルサイズがより大きくなります。
サンプルレートは44.1KHz、48KHz、96KHzなど(もっと大きな数値になっている場合もあります)の表記のされ方があり、
ビット深度は8bit、16bit、24bit、32bit…などの表記になっています。
あまりに高いビット深度とサンプルレートの音声データは、容量が大きいうえに再生するパソコンの性能にも注意が必要で、さらに人間の可聴域を極端に超えていると私たちにはその音が出ているのかわからない可能性があります。
周波数応答
マイクが拾った音をどこまで認識するかを表しています。
周波数で表示されるため、Hz(ヘルツ)という単位を使います。
人間が聴き取れる範囲(可聴範囲)である20~20000(20K)Hzの間で表示されていることが多いと思います。
この数字の幅が広いほど、音声を安定して認識してくれることになります。
最大SPL
マイクが受けられる最大の音の圧力(音圧)を示します。
単位はdBで表示されます。
この数値を超えた大きな音がマイクに入ると、音が割れる(歪む)か、ひどい場合にはマイクが壊れてしまいます。
よって、この数字が大きいほど音圧に対するマイクの耐久性が高い(大声や大きな音に耐えられる)ことを示しています。
SN比(信号対雑音比)
信号とノイズの比率を表す数値です。単位はdBです。
マイクの場合、概ね60~90dBの間くらいの数値になっていることが多いと思います。
この数値が大きいほど、雑音が少ない音になることを示しています。
購入時に比較して迷うようでしたら、SN比の数値が高いほうを選ぶという決め方もできます。
インピーダンス
機械間の抵抗を表していて、この数値が高いほどノイズが発生しやすくなります。よって数値が低いほうが優秀ということになります。
電気抵抗を表示するものなので、単位はΩ(オーム)で表示されます。
通常の声のやりとりで困ることは少ないと思いますが、ギターなど楽器で大きな音が発生する道具の場合、マイク側もそれに対応できるようにお互いの道具のマッチングが必要になります。
そういう意味では楽器類の使用をするときに気になる項目といえるかもしれません。
おわりに
長い長いマイクの記事、最後までお読みくださってありがとうございました。
記事を書きながら、マイクもたくさんの製品が出ていて、初めてマイクを選ぼうと思った時に本当に悩んで迷ったのを思い出しました。
今のマイクにたどり着くまでに私が調べて学んできたこと、そしていくつものマイクを実際に買って試してきた経験が、皆さんの問題解決のお役に立ったら嬉しいです。
あなたの声が本来持っている魅力が、今よりさらに多くの方へと届くマイクに出会えますように。